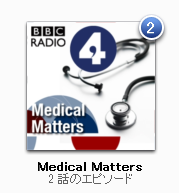やのっちです。
今日はごく個人的な話を。
いま回ってる科の飲み会でスーツを着る機会があったのですが、思わぬ発見が。
 |
| iPod nanoーーーーーー(初代)! |
なくしたと思って諦めていたiPod nanoーーーーーー!
てっきり落としたと思っていたらスーツの内ポケットに入っていました。
僕は医学部3年生のころに医学英語の授業で先生が「毎日医学系のpodcastを聞きなさい」とおっしゃっていた言葉に愚直に従って、毎日(、とは言いませんがほぼ毎日 笑)podcastを聞き続けているヘビーユーザーだったので、iPodが見当たらなくなったときはショックでした。
(ご存知かも知れませんが、podcastは「iPod+broadcast」かなにかの造語で、iTunesを通じたラジオやテレビ番組のようなものです。無料でダウンロードできます。)
先生に「早速今日から始めなさい。明日からではなく今日です」と言われたので帰りにiPodを買って帰ったら、翌日次世代機が発売されたという、ほろ苦い思い出もあるiPodです。
特に6年生になってからは少しだけ内容がわかるようになってきたので(馬の耳に念仏→石の上にも三年)、楽しくなって、家にいる間ほとんどずっとiPodを聞いて(聞き流して)いました。
「皿洗いしながら聞くBBCのニュースは最高!」というよくわからない価値観のもとせっせとダウンロードしては聞いていました(半分も聞き取れてないと思いますが)。
ここ数週間は、さしあたって皿洗いしながら聞くものがないと困る(?)ので、
①買ったけどあんまり使ってなかった(初代)iPadの内蔵スピーカーから音を出してみる。
→洗い物のときは水の音で聞こえないし、近所迷惑になるので深夜とかは聞けない。
②iPadを背中のところにくくりつけてiPodの代わりにしてみる。
→硬くて着け心地が悪いうえに、間からすべり落ちた時にコードに引っ張られたイヤホンがはずれて外耳道がきわめて痛い(カナル型恐るべし)。
③iPadはテーブルの上に置くことにしてBluetoothのイヤホンを装着する。
→これはまあまあ。起動時に接続が確立するまでに時々時間がかかるのと、状況によって接続が悪くなるのと、充電が早く切れるのとが玉に瑕だけど、暫定的にアリ!
ということで部屋を移動するたびにぶちっと切れるフラストレーションにも少し慣れてきたころに、まさかのiPod発見です!
こ、これはもしや… 困難にも耐えて、地道にpodcastを聞き続ける道を模索した僕に対する神秘的ないざないなのではないか、とも思えました(笑、というかそもそも酔っ払って内ポケットに入れたのを忘れてただけなんですけどね。出来事に意味を与えるのはよくも悪くも人間の作為~ 笑)。
ということで、久しぶりにiPod nano生活に戻って思ったのは、やっぱり安定した聴き心地と、胸ポケットに納まるサイズがよい、ということでした。わーい
(蛇足ですが、iPadだと2倍速再生ができて、これに関してはiPadの方が勝ると思います。2倍速のあとに普通のスピードで再生するとうそみたいに聞き取れます(といっても僕のリスニング力ではたかが知れてますが))。
******************
すみません、これからが本題(?)。
論文を検索したり読んだりするときにやっぱり英語が必要になると痛感する今日この頃ですが、僕なりのpodcast勉強法をご紹介します。
…といってもひたすら聞くだけです。わからなくても聞く。
文章を読むのだと、わからないといつまで経っても終わらなくていらいらするものですが、podcastならお皿洗ってる間に終わります。
内容?ぜんぜん覚えてませんよ(えっへん)。
でもそれが「自分の潜在知を養っているに違いない」と思い込んでいます。
「読書百篇意自ずから通ず」の境地ですね。
続けてるうちにうっすらわかるようになります。きっと。
やのっちが聞いているオススメpodcast
【第1位 NEJM This week】
いわずと知れた、あの超有名誌のおいしいところだけを厳選して、毎週聞かせてくれます!
このクオリティは、他の医学系podcastをぶっちぎりに突き放してます(と思っています)。
音質もいいし、安定感があります。絶対的にオススメ。
僕も「99%わかんなくてもいいからとりあえず聞いとこ!」というつもりで聞き始めて、本当に99%くらい聞き取れなくて泣きそうになりましたが、最近は少しわかるようになってきて嬉しいです。
(どうでもいいですが、フランス・イタリア・ドイツ語などの固有名詞を現地語読みしてるところが個人的に大好きです。)
【第2位 nature podcast】
広く自然科学系全般を扱ってる、超超超有名誌ですよね。
NEJMがあくまで学術的で上品な仕上がりであるのに対し、nature podcastはエンターテイメント性があり、聞いていて純粋に面白いです。
このブログの読者層を意識してあえての2位としました。
でも医学に関することも必ず取り上げられるので、購読して損はないはずです。
nature medicineなど、姉妹版もいくつかあるのでそちらもあわせてチェックしてみてください。
【第3位 Merck Manual】
僕がWeb上でいつもいつもお世話になっている、メルクマニュアルのpodcast版です。
すでに全回配信が終了しているので過去の放送をダウンロードしてます。
症候学の部分を対話形式のpodcastにまとめてくれているので、本当に勉強になります。
繰り返し聞きたい番組。
話し手の音声が右のイヤホンから、聞き手の音声が左のイヤホンから、と分かれているので、やや聞きづらいのが玉にキズ。
【第4位 Medical Matters】
BBCのラジオ番組はたくさんpodcastになっていますが、そのひとつと思われます(個人的にイギリス英語が大好きなので、BBCのpodcastはたくさん購読しています。ニュースとかも面白いですよ)。
医学・医療の話題を、特に社会的な見地から論じるような番組が多いですね。
社会学的・人文学的視点を持って医学・医療で何が起こっているのか見つめたい人にぴったり。
新聞で言うと3面記事のような感じかな?
【第5位 Science Friday】
同級生の友達に教えてもらって以来長く聞いているものです。
アメリカのラジオ番組で、話題の科学者をスタジオに迎えてリスナーから電話で質問を受けるというスタイルで、1時間くらいまったりお話する、なんとなく聞いていて安心する番組です。
リスナーは科学と縁のない仕事をしている一般人が多いので、思いがけない切り口からの質問が飛び出したりして面白いです。
科学全般を扱いますが、医学ネタもわりと扱ってくれていて勉強になります。
【番外編 101.comシリーズ】
英語を勉強することになれていると、英語を使って勉強することになかなか適応できませんよね。
僕が英語をツールとして認識できるようになったきっかけが、英語を通して(他の)外国語を学ぶということでした。
というのも、(たとえば)中国語を聞いてもよくわからないけど、英語の解説の方は(相対的に)よくわかるので、英語が聞こえてくると「よかった、英語だ。理解できる」という感情が湧くんです!
これって意外と重要なんじゃないかな、と思っているのですが、どうでしょう。
(ちなみに中国語はまだぜんぜん勉強できてません…頑張ります)
このシリーズ、大体何語でもあるので(日本語も)気になったのをとりあえず全部きいてみるのも面白いですよ。なんせ無料!
ということでだらだら長くなってしまいましたが、これにて今回は終わりますね。
オススメのiPod、iPad活用法(および、iPodをポケットから落としても外耳道にやさしいイヤホンなど)をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメントやfacebookを利用して、あるいは直接教えてください。
ではまたー